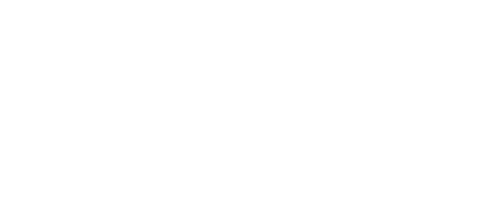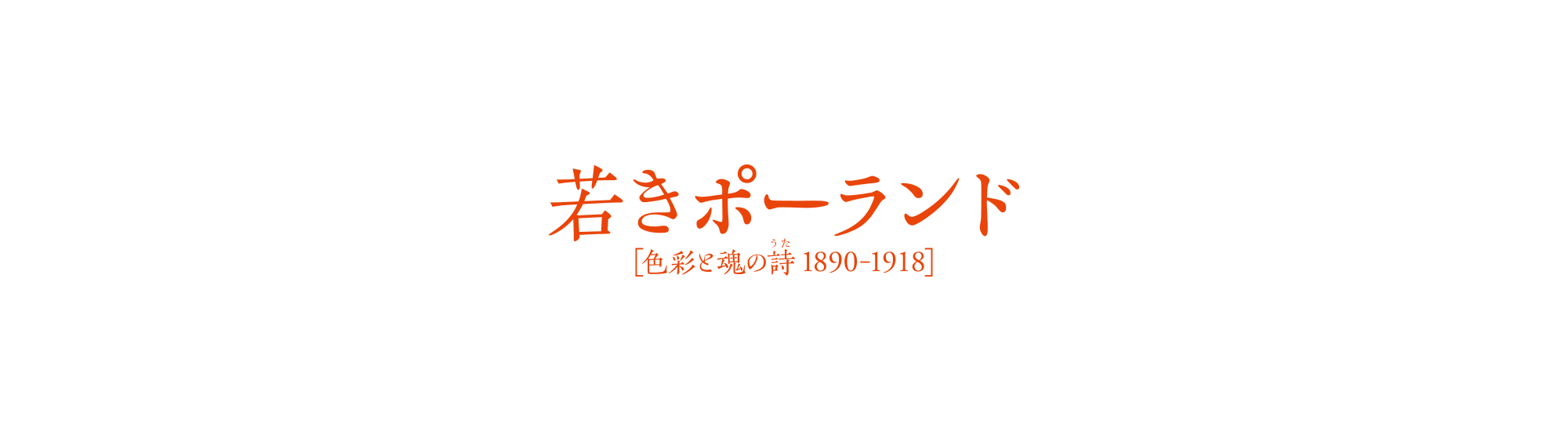
スペシャル [Special]
本展公式Xフォロー&リポストキャンペーン
本展X公式アカウント(@youngpoland2025)をフォロー&該当の投稿をリポストいただいた方の中から抽選で10組20名様に本展無料オンラインチケットが当たります!
応募期間:2025年1月23日(木)-2月6日(木)
- ※本キャンペーンの応募要項ならびに注意事項をお読みのうえご応募ください。
このジュニアガイドは、
〈若きポーランド〉―色彩と魂の詩 1890-1918 の鑑賞の手引きとして、
小学校高学年から中学生を対象に作成しました。
ポーランドは、ヨーロッパの中央にあり、たくさんの国とバルト海に囲まれています。国名の「ポーランド」(ポーランド語でPolska)は、ポーランド語の「平原/pole」ということばが語源となっています。バルト海の美しい海岸、数多くの川や湖、たくさんの山々、さらには広い砂丘、森など素晴らしい景色が広がる自然の魅力にあふれた国です。
古都・クラクフは中世からの世界をそのまま残した街なみが魅力で、世界中からの観光客でいつもにぎわっています。
ポーランドの首都はワルシャワで、ピアニストで作曲家のショパンが育ったところとして有名です。
ポーランドは1795年、プロイセン・オーストリア・ロシアの3国によって占領されてしまいました。なんとそこから再びポーランドとして独立を取り戻す1918年までには、123年という長い時間がかかります。
国を失った人々がポーランド人としてのささえとしたのが、文学や音楽そして絵画などの芸術でした。とくに19世紀の後半、文化の中心地クラクフにあった美術学校で校長をしていた画家ヤン・マテイコのもとからは、数多くの若い芸術家たちが巣立ちました。
彼らは〈若きポーランド〉と呼ばれ、ポーランドの伝統文化も学び、ポーランドの国民芸術とはどんなものかを探していきました。
スタニスワフ・ヴィスピャンスキ[デザイン]
アントニーナ・シコルスカ・キリム工房、チェルニフフ[製作]
《キリム》
1904年、羊毛、キリム技法、葦入りの織物、クラクフ国立博物館蔵
オルガ・ボズナンスカ
《菊を抱く少女》
1894年、油彩/厚紙、クラクフ国立博物館蔵
ヤン・マテイコ[原画]
イグナツィ・ウォピェンスキ[銅版画]
《自画像》
1893年[原画:1892年]、エッチング/紙、クラクフ国立博物館蔵
〈若きポーランド〉の芸術家たちに広く影響をあたえた日本美術との関係にも注目!
江戸時代後期の浮世絵師葛飾北斎や歌川広重の作品など日本美術を愛したフェリクス・"マンガ"・ヤシェンスキは、自分の愛称に「マンガ」と名づけるほどに日本美術の大コレクターでした。
クラクフで開催したヤシェンスキのコレクションの展示会は、ポーランド美術に日本趣味がもたらされるきっかけのひとつとなり、〈若きポーランド〉の画家たちも彼のコレクションを作品に描いています。
《日本の屏風の前で三味線を持つ》
フェリクス・ヤシェンスキ
1906年以前、写真、クラクフ国立博物館蔵
歌川広重
神奈川八景より「内川暮雪」
1840年頃、木版/紙、クラクフ国立博物館蔵
ユリアン・ファワト
《冬景色》
1915年、油彩/カンヴァス、クラクフ国立博物館蔵
歌川広重
名所江戸百景 第27図「蒲田の梅園」
1857年、木版/紙、クラクフ国立博物館蔵
ヤン・スタニスワフスキ
《プランティ公園の断片》
1905年頃、油彩/厚紙、クラクフ国立博物館蔵
こんな機会は二度とない?!
絵画、版画、家具や工芸品をふくむ約130点のポーランド美術作品が展示される本展覧会。
特別にその一部をご紹介します!!
18世紀末に他国に占領され、国がなくなってしまった時代。画家たちは、かつてのポーランドの歴史や伝説を描きました。
ヤツェク・マルチェフスキ
連作『ルサウキ(ルサールカたち)』より「憑依」
1887年、油彩/カンヴァス、ヤギェロン大学付属博物館蔵、クラクフ国立博物館蔵
ヤン・マテイコ
《〈スタンチク〉草稿》
1861年、油彩/カンヴァスの上に紙、ワルシャワ国立博物館蔵
ヤン・マテイコ
《ミコワイ・コペルニク:〈天文学者コペルニク、あるいは神との会話〉のためのスケッチ》
1871年、油彩/厚紙、クラクフ国立博物館蔵
ヤン・マテイコ
《1683年、ウィーンでの対トルコ軍勝利伝達の教皇宛書簡を使者デンホフに手渡すヤン3世ソビェスキ》
1880年、油彩/カンヴァス、クラクフ国立博物館蔵
ヴワディスワフ・ポトコヴィンスキ
《ルピナスの野》
1891年、油彩/カンヴァス、クラクフ国立博物館蔵
スタニスワフ・ヴィトキェーヴィチ
《冬の巣》
1907年、油彩/カンヴァス、クラクフ国立博物館蔵
独自の表現で、ポーランドの雄大な自然や冬の風景を描いた〈若きポーランド〉の画家たち。中には日本の浮世絵に似ているものも?!
スタニスワフ・カモツキ
《チェルナの僧院の眺め》
1908年頃、油彩/カンヴァス、クラクフ国立博物館蔵
ヤン・スタニスワフスキ
《水辺のポプラ》
1900年、油彩/カンヴァス、クラクフ国立博物館蔵
レオン·ヴィチュウコフスキ
《日本女性》
1897年、油彩/カンヴァス、クラクフ国立博物館蔵
ユゼフ・パンキェーヴィチ
《日本女性》
1908年、油彩/カンヴァス、クラクフ国立博物館蔵
オルガ・ボズナンスカ
《日本女性》
1889年、油彩/樫板、ワルシャワ国立博物館蔵
ポーランドの芸術家たちは、ヤシェンスキと彼の日本美術コレクションを通して、日本美術に対する理解を深めました。着物姿の女性や、浮世絵の構図で描かれた作品など、日本の文化を感じる絵画が多くみられます。
クラクフ国立博物館にある日本の美術品
歌川広重
《名所雪月花より「井の頭の池弁財天の社雪の景」》
1842-45年、木版/紙、クラクフ国立博物館蔵
作者不詳
《鶴亀形蝋燭立》
1880-88年、鋳造、彫金、緑青、ブロンズ、クラクフ国立博物館蔵
礒田湖龍斎
《鷺娘》
1772-75年、木版/紙、クラクフ国立博物館蔵
郊外の農村や地方の素朴かつ広大な風景、そして色彩豊かな伝統文化や習慣はポーランドの魅力のひとつです。その地方の伝統や文様を取り入れた新しいデザインの家具や布模様などがたくさんあります。
スタニスワフ・ヴィスピャンスキ[デザイン]
ザヨンチェク&ランコシュ、ケンティ[布地製作]
ヘレナ・チェレムガ[刺繍]、
《刺繍のあるタペストリー(ペルメット)》
1903-04年、ウール、平糸刺繍、クラクフ国立博物館蔵
マリア・ワベンツカ
《ザコパネ様式によるドレス》
1900年頃、機械・手縫い、手刺繍、フェザー・ステッチ、バックステッチ、アップリケ、布、ウール糸、クラクフ国立博物館蔵
カジミェシュ・ブジョゾフスキ[デザイン]
アントニーナ・シコルスカ・キリム工房、チェルニフフ[製作]
《キリム》
1906年以前、羊毛、麻、キリム技法、葦入り織物、クラクフ国立博物館蔵
スタニスワフ・ヴィスピャンスキ[デザイン]
アンジェイ・スィドル[製作]
《椅子:ゾフィア&タデウシュ・ジェレンスキ夫妻邸のための家具セットより》
1905年、松材、トネリコ材、トネリコの化粧板仕上げ、布張り、クラクフ国立博物館蔵
アントニ・ヴォイチェホフスキ
《婦人用編み上げブーツ》
1904年、皮革、機械縫い、アップリケ、クラクフ国立博物館蔵
《マクフ・ポトハランスキ国立刺繍学校ハンドバッグ》
1900年、刺繍、手縫い、フェザー・ステッチ、サティン・ステッチ、ボタンホール、ステム・ステッチ、リネン、繭綿、ラフィアヤシ、刺繍用毛糸、クラクフ国立博物館蔵